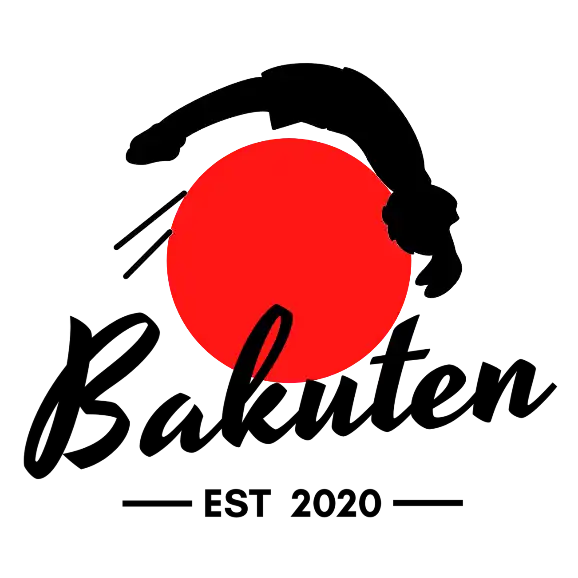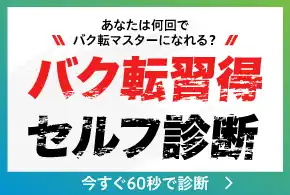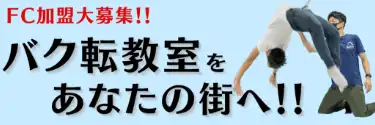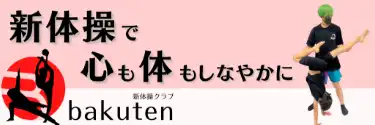ブログ
2025.06.30
後転のコツはある?うまくできない原因や練習方法についてご紹介!

マット運動で前転ができるようになったら、後転に挑戦してみましょう。
後転は前転より少し難しく、後ろに回る恐怖心や、失敗してしまったときの痛さから、後転がなかなか上手にできないというお子さんも珍しくありません。
後転が成功せずに悩んでしまうお子さんも多いですが、実は、いくつかのコツをマスターするだけで、簡単に後転ができるようになります。
後転ができなくてお悩みのお子さんや保護者の方は、ぜひこの記事を読んで後転の安全な練習方法などを参考にしてみてくださいね!
⇒前転のコツはある?うまくできない原因や練習方法についてご紹介!
後転ができない原因は?よくある失敗パターン
前転ができるようになり、次の技に挑戦するといえば、後転です。
しかし、後転は回るときに後ろが見えないため、恐怖心を抱いてしまうお子さんも多いです。
また、一度失敗してしまったことで怖くなってしまい、克服できずに落ち込んでしまうお子さんもいます。
後転ができないのには、必ず原因があります。
なぜそのようなミスが起こるのか、よくある失敗パターンをご紹介しますので、お子さんの状態と照らし合わせてみてくださいね。
原因①:手でしっかり押せていない
手でしっかりマットを押せず、回転が止まってしまい、失敗してしまうケースは多いです。
両方の手の平をしっかり広げて、マットを力強く押すことで、回転力がよりアップします。
お子さんの手がマットを押すことができているか、まずは確認してみましょう。
原因②:体が固くて丸まれない
後転をする際は、背中・首・股関節の柔軟性が重要です。
体が固いとスムーズに回ることはむずかしく、怪我にもつながってしまいます。
体の柔軟性が低いのに無理な動きをしようとすると、首から背中にかけて負担がかかりやすいので注意が必要です。
柔軟性を高めるためには、ストレッチを取り入れましょう。
原因③:首が伸びてしまう(あごを引いていない)
首を伸ばしたままにしてしまうと、頭から落ちてしまい回転しづらくなるという失敗例もあります。
あごを引いていない状態だと、首の位置が不安定になり、回ろうとしたときに指や頭をぶつけてしまう可能性があります。
あごをしっかり引いて、おへそを見ることで、体を丸めやすくなり、後転がしやすくなります。
原因④:後ろに倒れるのに恐怖心がある
後ろが見えないのに後ろの方向に倒れることに対して、恐怖心を抱いているのが原因なことも考えられます。
お子さんの恐怖心を克服するには、大人の声掛けが大切です。
小さな成功体験を積み重ね、「今のところよかったよ」「一緒にやってみよう」など、お子さんの成功をともに喜び、小さな成功をお子さんの自信につなげていきましょう。
後転の正しいやり方
これまで、後転ができない原因や失敗例についてご紹介してきました。
正しいやり方で後転を行うためには、後転の基本の流れを理解することが重要です。
後転はしゃがんだ状態から後ろに転がり、手で体を押しながら、最終的には足の裏を地面につけて立ち上がる姿勢で周り切ります。
正しいやり方を紐解いていくことで安全かつ簡単に後転ができるようになるので、これからご紹介する後転のステップをぜひ参考にしてみてください。
ステップ①:しゃがんだ姿勢で準備
まずはじめに、しゃがんだ姿勢で準備しましょう。
後転では、手を耳の横にスタンバイしておくことが重要です。
ステップ②:体を丸めて、後ろに転がる
おへそを見るようにして、体を丸め、後ろに転がりましょう。
太ももとお腹の間に少しすき間を作ることで、より体が回りやすくなります。
しっかりと体を丸めて、手を床に付けるように回転することに意識をしてみましょう。
ステップ③:両手で床を強く押す
後ろに回転したら、手のひらと足先が床に付きます。
ついたタイミングで、立ち上がる動作をしながら、手の平で床を強く押しましょう。
床をしっかり押す動作ができると、よりスムーズに立ち上がりやすくなり、綺麗な後転ができるようになります。
両手の手のひらで床をグッと押して、体が前のめりにならないように支えましょう。
ステップ④:しっかり立ち上がってフィニッシュ
後転では、立ち上がった姿勢でフィニッシュになります。
ステップ③の動作で前に倒れてしまったり、膝をついてしまわないように何度も繰り返し練習しましょう。
後転がうまくなる4つのコツ
後転は、先ほどのやり方の流れを抑えることで徐々にできるようになりますが、早く・うまくなるには、4つのコツがあります。
コツをつかんで、ひとつずつクリアしていくことで、後転は上達します。
ひとつひとつできているか確認しながら練習してみてください。
コツ①:あごを引いておへそを見る
あごを引いておへそを見ましょう。
頭を床につけないようにすることは、後転の基本の姿勢です。
あごを引くことで自然に背中が丸まり、転がりやすくなります。
コツ②:手のひらを床につけて、地面を押すことを意識
後転では手に床を押すことが「立ち上がるきっかけ」になり、これにはタイミングや力加減が重要です。
背中を丸めて転がる途中、手のひらを床に付けて、しっかりと地面を押すことを意識しましょう。
コツ③:背中を丸めて転がる
背中を丸めて転がることで、丸めた背中が勢いをつけてくれます。
おへそを見るようにしてあごを引き、ボールになるような感覚で背中を丸くして転がりましょう。
体を丸く保つことで、転がりやすく、首の負担も減らすことができます。
コツ④:丸まった形から手足を伸ばす
回転には体を丸める動作が大切ですが、しっかりと立ってフィニッシュするためには立ち上がる動作で手足をしっかり伸ばすことが大切です。
手足の伸ばしが足りなかったり、途中で脱力したりするとうまくフィニッシュできなくなってしまいます。
地面を手で押しながら上体を起こし、同時に足を伸ばしてまっすぐ立つことを意識しましょう。
自宅でもできる後転の練習方法
ここでは最後に、自宅でも安全に後転を練習するためのトレーニング方法をご紹介します。
少しずつ練習を積み重ね、成功体験を繰り返して自信をつけることで、学校の授業でも苦手意識を軽くしてマット運動に取り組めるかもしれません。
後転ができるようになると、さらに応用した技にも挑戦できるようになるので、これらのトレーニングは日常的に取り組むと良いでしょう。
練習方法①:首・背中・股関節の柔軟運動
首の柔軟運動はゆっくりと時計回りと反時計回りに回しましょう。
また、右手をあげて頭の上を通り、左耳の上に添え、ゆっくりと首を右側に倒して首筋をのばす動作も効果的です。左も同様に行ってください。
背中の柔軟は、「だるまさんポーズ」と呼ばれるポーズがおすすめです。仰向けに寝て両膝を胸に引き寄せ、腕で抱え込んで背中を丸めます。
また、四つん這いになって背中を丸めたり反らせたり、猫のポーズを行うことで、背骨の柔軟性が高まります。
股関節の柔軟体操では、床に座り、左右の足の裏を合わせた状態で、膝を上下に動かしたり、背筋を伸ばしたり、上半身を前に倒してみてください。
この際、深呼吸をしながら行い力を抜くことが大切です。
練習方法②:ゆりかご
ゆりかごは、丸まった姿勢を保ち、後ろに転がって戻る動作のことです。
あごを引いて、体を前後に揺らすことで、回転の感覚と、起き上がる際に使うお腹の力を意識することができるようになります。
ゆりかごでは、後転の形を自然に体で覚えることができ、背中で回る感覚や姿勢の安定感をつかむための動きにつながります。
練習方法③:背支持倒立
背支持倒立とは、倒立の技の基本の動作で、背中で体を支えながら足をまっすぐ上に伸ばす姿勢のことを指します。
床に仰向けになったら、ひざを曲げて両足を胸に引き寄せ、腰を浮かせながら背中と肘で体を支えてください。
手で体をしっかりと支えながら、足をそろえて上に向かって伸ばし、バランスを保ちましょう。
手で地面を押す力と足を高く持ち上げる意識を身に着けることができます。
練習方法④:補助つきで練習する
ストレッチや動作のイメージがつかめるようになったら実際に後転を練習してみましょう。
初めのうちは補助つきで練習することで、安心して後転ができます。
お子さんの恐怖心が和らぐので、声掛けしながら行うのがおすすめです。
補助者は、頭が床に付かないように注意しながら腰のあたりをしっかりと持ち、転がる動作を優しくサポートします。
サポートする際は力を入れすぎないように調節しましょう。
練習方法⑤:スロープを使う
床に傾斜を付けることで、回転のサポートがしやすくなり、恐怖心も軽減されます。
また回転時に勢いがついて、より回転しやすくなる効果もあります。
自宅で練習する際には、クッションや布団を重ねて傾斜を作る方法がおすすめです。
後転のコツ・練習方法!うまくできない原因も解説|まとめ
この記事では、後転のコツやうまくできない原因について解説してきました。
後転に失敗してしまうのには、必ず原因があります。
記事の中でご紹介したコツを意識して練習することで、後転マスターへ近づくことができるので、正しいやり方とコツを参考にして少しずつ練習を重ねていくようにしましょう。
後転だけでなく「もっと難易度の高い技に挑戦してみたい」「もっといろいろな技をできるようになりたい」と思った方はバク転パーソナル教室に通うのもおすすめですよ!